高度専門職1号ハを保有し、永住等を計画されている方へ重要なお知らせです。2025年10月16日に施行された経営・管理ビザの基準省令改正により、永住許可申請時には改正後の新基準(資本金3,000万円、常勤職員1名以上、日本語N2相当など)への適合が必須となりました。多くの方が誤解されているようですが、在留期間更新には3年間の経過措置がある一方で、永住申請や高度専門職2号への変更には経過措置が適用されません。つまり、ポイントが80点あっても、資本金が500万円のままでは永住申請が不許可となるリスクが極めて高い状況です。本記事では、既存保持者が直面する深刻なリスクと、今すぐ取るべき具体的な対策を京都の行政書士が詳しく解説します。
2025年10月改正で何が変わったのか?高度専門職1号ハへの影響
経営・管理ビザ基準省令改正の概要
2025年10月16日、出入国在留管理庁は「経営・管理」在留資格の上陸基準省令を大幅に改正しました。最も大きな変更点は、資本金要件が従来の500万円から6倍の3,000万円に引き上げられたことです。さらに、これまで「2名雇用で資本金代替可能」だった雇用要件も厳格化され、常勤職員1名以上の雇用が必須となりました。加えて、申請者本人もしくは常勤職員に日本語能力試験N2相当の語学力が新たに求められるようになり、実務経験についても「修士号または3年以上の経営管理実務(スタートアップビザによる準備期間も参入可能)」という明確な基準が設けられました。これらの変更は実質的に「小規模事業での経営管理ビザ取得」が困難となり、一定規模以上の投資と事業実態を持つ企業経営者のみを受け入れる方針への転換を意味しています。
なぜ高度専門職1号ハも影響を受けるのか?
多くの方が誤解されているのですが、高度専門職1号ハは「ポイントさえ70点以上あれば良い」わけではありません。入管法の構造上、高度専門職1号ハは「経営・管理」の上陸基準を準用しているため、ポイント計算の前段階として、経営・管理ビザの基準(資本金・雇用・語学など)を満たすことが大前提となっています。つまり、いくらポイントが80点、90点あっても、「土台となる上陸基準」を満たしていなければ、申請自体が門前払いとなります。今回の改正は、この「土台部分」が大幅に引き上げられたため、高度専門職1号ハの新規取得・更新・永住申請・2号変更のすべてに影響が及びます。特に、改正前の「資本金500万円スキーム」で1号ハを取得した既存保持者にとって、この変更は将来設計を根底から覆す深刻な問題となっています。
【最重要】永住申請には経過措置が適用されない
更新と永住・2号変更の扱いの違い
今回の改正で最も注意すべき点は、申請の種類によって「経過措置の適用有無」が異なることです。法務省は、既存の経営・管理や高度専門職1号ハの在留資格保持者に対して2028年10月15日までの3年間の経過措置を設けていますが、これは「在留期間更新許可申請(1号ハ→1号ハの単純更新)」にのみ適用されます。一方で、永住許可申請や高度専門職2号への変更申請は、経過措置の対象外とされています。つまり、現在資本金500万円で1号ハを保有している方でも、2028年10月15日までの3年間は「更新するだけ」なら当面は問題ありません(※)が、「永住を取りたい」「2号に変更したい」と思った瞬間に、新基準(3,000万円等)への適合が求められるという、非常に厳しい状況になっています。この区別を理解していないと、準備不足のまま永住申請して不許可となり、再申請が困難になるリスクがあります。
出入国在留管理庁の公式見解
法務省・出入国在留管理庁が公表した公式文書には、極めて明確な記載があります。「令和7年(2025年)10月16日以降に行う永住許可申請については、改正後の許可基準に適合していない場合は、在留資格『経営・管理』、『高度専門職1号ハ』又は『高度専門職2号』からの永住許可申請は認められません」(法務省在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について)。この文言は、既存在留資格保持者であっても、永住申請時点で新基準を満たしていなければ不許可となることを意味しています。さらに、「施行日前に受理された申請」については旧基準で審査されますが、2025年10月16日以降に新たに行う申請はすべて新基準適用です。つまり、現時点(2025年11月以降)から永住申請を検討されている方は、すでに「駆け込み」の猶予期間を過ぎており、新基準への対応が必須となっています。
永住不許可となるケース:あなたは該当していませんか?
チェックリスト形式で自己診断
ご自身の会社・事業の状況が永住申請の新基準に適合しているか、以下のチェックリストで確認してください。以下の項目に1つでも該当する場合、現状のままでは永住不許可となるリスクがあります。
-
☐ 会社の資本金が3,000万円未満である
-
☐ 常勤職員(フルタイム雇用)が1名もいない(外注やパートタイムのみ)
-
☐ 日本語能力試験N2相当の資格を保有していない。またはその条件を満たす常勤職員を雇用していない
-
☐ 直近の決算書で赤字または債務超過の状態である
-
☐ 税金(法人税・源泉所得税・住民税等)に未納や遅延がある
-
☐ 社会保険料(厚生年金・健康保険)の支払いに遅れがある
-
☐ 過去5年以内に交通違反や刑事事件の記録がある
特に上の3項目(資本金・雇用・日本語)は今回の改正で新たに追加された要件です。これまで「ポイントさえあれば問題ない」と考えていた方も、これらの基準を満たさなければ永住への道が閉ざされてしまいかねません。
改正後考えられる不許可事例
今回の省令改正を受け、これから起きるであろう不許可事例の中には、深刻なケースが複数あります。例えば、「ポイント80点、日本在留1年経過で永住申請したものの、資本金が500万円のままだったため不許可となるケース」や、「常勤雇用がゼロ(業務委託のみで運営)で高度専門職2号への変更を申請し、却下されるケース」などが考えられます。不許可の履歴は入管のシステムに記録され、再申請時の審査に影響があると考えられます。そのため「とりあえず申請してみる」という安易な判断は、将来のビザ取得機会を狭める可能性もあるので、事前に要件を満たしてから申請することが確実な永住取得や2号への移行へのか確実かつ唯一の道と言っても良いでしょう。
いつまでに永住申請すれば間に合うのか?タイムリミットの検証
「施行日前の申請」は既に間に合わない
多くの方から「いつまでに申請すれば旧基準で審査されますか?」というご質問をいただきますが、残念ながらそのタイムリミットは既に過ぎています。法務省在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正についてによれば、2025年10月16日(施行日)より前に入管へ申請書類を受理された案件については、旧基準(資本金500万円等)で審査されます。しかし、現在は2025年11月下旬であり、施行日から1ヶ月以上が経過しています。したがって、今から新規に永住申請を行う場合は、すべて改正後の新基準(資本金3,000万円等)が適用されることになります。「もう少し早く知っていれば…」と悔やまれる方も多いです。今回の省令改正の情報はかなり遅かったうえにかなり急な日程で行われたため、対応する余裕がほとんどなかったといえます。今後は、新基準を満たすための準備(増資・雇用・事業計画修正)に集中することが現実的な選択肢となります。
「駆け込み申請」のリスク
では、「要件を満たしていなくても、とりあえず申請だけしておく」という選択肢はどうでしょうか?結論から申し上げると、これは極めて危険な行為です。要件を満たさないまま申請すると、当然ながら不許可となりますが、その記録は入管のシステムに残りますので場合によっては再申請時の審査でマイナス材料となりかねません。また不許可処分を受けた後の再申請までの間にビジネス環境が変化するリスクもあります。さらに、審査には通常6〜12ヶ月かかるため、その間に会社の業績が悪化したり、家族構成が変わったりすると、さらに複雑な事態となります。確実な許可を得るためには、要件を完全に満たしてから申請することが不可欠です。
対策1:資本金を増資して新基準をクリアする
増資のメリットとデメリット
最も確実な対策は、会社の資本金を3,000万円まで増資することです。メリットは明確で、永住申請・高度専門職2号への変更・将来的な事業拡大のすべてにおいて道が開けます。また、取引先や金融機関からの信用力も大幅に向上し、融資や契約交渉が有利になることもあります。一方、デメリットとしては、まず資金調達の負担が挙げられます。2,500万円という大金を用意するのは容易ではなく、親族や本国からの送金、既存事業の利益留保など、資金源を明確に証明する必要があります。税務上も、増資に伴う登録免許税や、資金の出所証明(Source of Funds)の準備が必要です。特に、「見せ金(一時的に借りて増資後すぐに引き出す)」は大きな問題となるため、絶対に避けなければなりません。増資は「永住のため」だけでなく、事業の成長戦略の一環として位置づけることが重要です。
増資手続きの流れと行政書士のサポート範囲
資本金増資の基本的な流れは以下の通りです。①株主総会で増資決議を行い、②新株発行または株式割当を実施し、③資金を会社口座に払込み、④法務局で変更登記を行い、⑤入管へ「所属機関等に関する届出」を提出します。この一連の手続きには、司法書士(登記)、税理士(税務申告)、行政書士(入管届出・ビザ申請)の連携が不可欠です。当事務所では、増資に伴うビザリスクの事前評価、資金源証明の準備支援、入管への届出書作成を一括してサポートいたします。特に重要なのは、増資後すぐに永住申請するのではなく、少なくとも3〜6ヶ月間は増資後の資本金で事業を継続し、決算書や納税実績を蓄積することです。入管は「形式的な増資」ではなく「実質的な事業実態」を審査するため、焦らず計画的に進めることが成功の鍵です。
対策2:高度専門職1号ハを更新し続ける(現状維持戦略)
経過措置を活用した「永住を諦めず待つ」選択肢
すぐに3,000万円を用意できない方には、「とりあえず経過措置を活用して1号ハを更新する」という現実的な選択肢があります。前述の通り、在留期間更新許可申請には2028年10月15日までの3年間、経過措置が適用されます。この期間内であれば、資本金500万円のままでも事業の継続性や納税実績が良好であれば更新が認められる可能性があります(ただし無条件で前の基準適用というわけではないことに注意が必要なのは前述の通り)。この戦略のメリットは、焦って無理な増資をせず、事業を着実に成長させながら、自然に3,000万円基準をクリアできるタイミングを待てることです。例えば、今後3年間で事業が軌道に乗り、利益が蓄積されれば、その利益を原資として増資することで、「見せ金」ではない健全な財務体質を示せます。ただし、この戦略を選ぶ場合は更新時に「事業の成長実績」を入管にしっかり示し、経過期間内に条件をクリアする見込みがあると伝えることが重要です。売上推移、従業員数の増加、取引先の拡大など、前向きな経営姿勢を伝えましょう。
1号ハと2号の実質的な差
「高度専門職2号にならないと不利なのでは?」と心配される方も多いのですが、実は1号ハと2号の実質的な差はそこまでではなく限定的です(もちろん大きいことは事実ですが)。2号の最大のメリットは「在留期間が無期限」であることですが、1号ハでも5年の在留期間が付与されるため、更新手続きは5年に1回で済みます。また、2号は「活動制限がほぼない」とされますが、他の高度専門職と異なり、ハの経営者の場合そもそも自社経営が中心なので、この恩恵を受ける場面は少ないといえます。一方、2号への変更申請には新基準(3,000万円)が適用されるため、無理に2号を目指して不許可となるリスクを考えると、「まずは1号ハで安定的に更新することを目指す方が賢明」というケースも多いと思われます。永住権についても、1号ハのまま(ポイント80点で在留1年、70点で在留3年)要件を満たせば申請できます。つまり、2号は「必須」ではなく「選択肢の一つ」と考えると良いでしょう。
対策3:永住以外の選択肢を検討する
帰化申請との比較
永住権取得が困難な場合、「帰化申請(日本国籍取得)」という選択肢もあります。帰化と永住の最大の違いは、帰化には「在留資格の基準(資本金3,000万円等)」が直接的には適用されない(と現状はされている)点です。帰化の要件は、①5年以上の継続在留、②20歳以上で本国法でも成人、③素行善良、④生計維持能力、⑤国籍喪失(日本国籍取得により本国籍を失う)、⑥思想善良(憲法遵守)などです。経営者の場合、「生計維持能力」は事業の継続性と納税実績で判断されますが、資本金の額そのものは(今のところ)絶対要件ではありません。ただし、帰化には「本国籍を失う」という重大なデメリットがあり、家族の意向や本国での財産管理、将来的な帰国の可能性などを慎重に検討する必要があります。また、手続きには通常1年前後かかり、面接や書類審査も厳格です。永住と帰化のどちらが適しているかは、個人の価値観と生活設計によって異なります。
配偶者ビザ(日本人・永住者の配偶者等)への変更
もし配偶者が日本人または永住者である場合、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」への在留資格変更を検討する方法もあります。これらの配偶者ビザには、経営・管理ビザのような「資本金要件」「雇用要件」は存在しません。配偶者ビザを取得すれば、就労制限がなくなり、事業の規模に関わらず自由に経営活動を続けられます。ただし、配偶者ビザの審査では「婚姻の実態(同居・生計一体・相互扶助)」が厳格にチェックされるため、形式的な結婚や別居状態では許可されない可能性があります。また、配偶者ビザから永住申請する場合、通常3年以上の婚姻実態と1年以上の日本在留が必要です。経営者としての在留にこだわりたい方には向きませんが、「家族との生活を最優先したい」という方には現実的な選択肢となります。
よくある質問(FAQ)
Q1: 経過措置は永住申請にも使えますか?
いいえ。経過措置(2028年10月15日まで)は「在留期間更新許可申請」にのみ適用されます。永住許可申請や高度専門職2号への変更申請には経過措置が適用されず、改正後の新基準(資本金3,000万円、常勤職員1名以上、日本語N2相当など)を満たす必要があります。つまり、現在資本金500万円で1号ハを保有している方でも、更新は可能ですが、永住や2号への変更は新基準をクリアしなければなりません。この点を誤解されている方が非常に多いため、ご注意ください。
Q2: 資本金500万円のままで永住申請したらどうなりますか?
2025年10月16日以降に永住許可申請を行う場合、改正後の新基準に適合していることが必須です。資本金が3,000万円未満の状態で申請すると、不許可となる可能性が極めて高いです。確実な許可を得るためには、要件を完全に満たしてから申請することを強くお勧めします。
Q3: 高度専門職2号への変更も新基準が必要ですか?
はい、必要です。高度専門職2号への変更申請も、永住申請と同様に経過措置の対象外です。変更申請時点で、改正後の基準(資本金3,000万円、常勤職員1名以上、日本語N2相当など)への適合が求められます。2号のメリット(在留期間無期限、活動制限なし)は魅力的ですが、新基準を満たせない場合は、無理に2号を目指すよりもまずは経過措置を活用して1号ハで更新する方が安全だと思われます。1号ハでも5年の在留期間が付与されるため、実質的な不便はそれほどありません。
Q4: ポイントが80点あっても不許可になりますか?
はい、あり得ます。高度専門職1号ハは「ポイント70点以上」が要件ですが、その前提として「経営・管理の基準」を満たす必要があります。いくらポイントが80点、90点あっても、土台となる基準(資本金3,000万円、常勤職員1名以上、日本語N2相当など)を満たしていなければ、永住申請は不許可となります。これは入管法の構造上、「ポイント計算」と「基準」が別々に審査されるためです。多くの方が「ポイントさえあれば大丈夫」と誤解されていますが、両方をクリアして初めて許可となることを理解しておいてください。
Q5: いつまでに増資すれば間に合いますか?
永住申請の「直前」に駆け込み増資をしても、入管は「形式的な増資」と判断するリスクがあるかもしれません。理想的には、永住申請の3〜6ヶ月前には増資を完了し、増資後の資本金で事業を継続している実態(決算書・納税実績・従業員給与支払い履歴など)を示すことが重要と思われます。特に増資直後に資金が流出していたり、事業実態が伴っていなかったりすると、「見せ金」を疑われて不許可となる危険があります。余裕を持った計画を立てましょう。
まとめ
高度専門職1号ハからの永住申請は、2025年10月改正により大きな転換点を迎えました。既存保持者の方々にとって、現状維持(経過措置を活用した更新継続)か、増資(新基準への適合)か、それとも別の道(帰化・配偶者ビザ)を選ぶかは、事業状況・家族構成・将来計画によって最適解が異なります。
最も危険なのは、「なんとかなるだろう」と楽観視して準備不足のまま永住申請し、不許可となることです。一度不許可になると、その記録が残り、再申請のハードルが上がることも考えられます。
当事務所では、お一人おひとりの状況に応じた戦略立案をサポートしています。「自分の会社は永住申請できるのか?」「増資すべきか、待つべきか?」など、少しでも不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。専門家として、確実な許可取得への道筋を一緒に考えます。
省令原文・公式資料リンク
→高度専門職・高度人材ビザ完全ガイドはこちら→高度専門職1号とは?メリット・申請条件・取得のコツを徹底解説についてはこちら
→高度専門職・高度人材ビザの家族帯同と特定活動を徹底解説の詳細はこちら
→高度専門職・高度人材が受けられる優遇措置とメリット完全ガイドはこちら

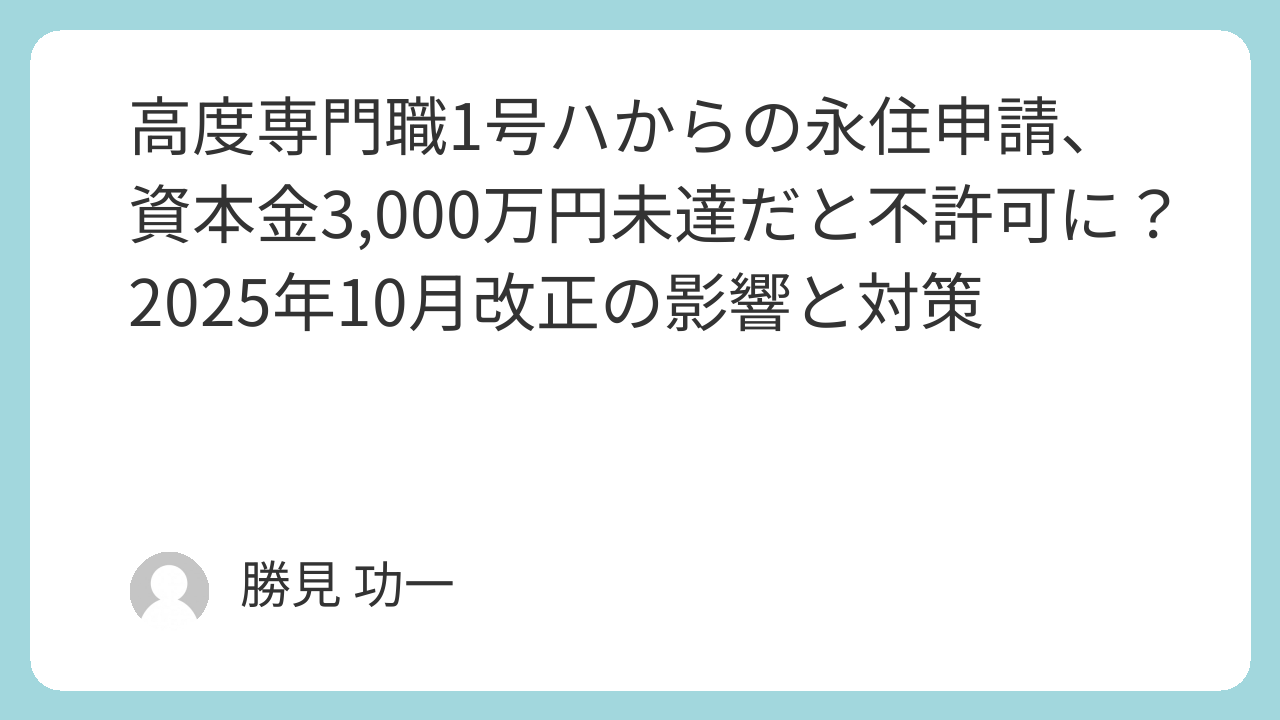
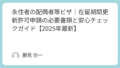
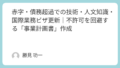
コメント