平日 9:00~17:00(土日祝対応あり)
メールは365日24時間受付 無料相談は土日祝対応
平日 9:00~17:00(土日祝対応あり)
メールは365日24時間受付 無料相談は土日祝対応

日本で外国人が働くためには、その活動内容に応じた「就労ビザ」と呼ばれる在留資格を取得する必要があります。一般的に「ビザ」というと入国許可証である査証(VISA)を指すこともありますが、ここでいう就労ビザは日本に滞在し働くための資格(在留資格)のことです。日本で働くための就労ビザは全16種類あり、2024年3月には特定技能における新たな4分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)の追加など重要な制度改正が行われました。本記事ではそれぞれの就労ビザの特徴や取得要件、在留期間などについて最新の情報を踏まえて解説します(詳細な解説は個別の解説ページにて)。外国人採用を検討している企業の人事担当者や日本での就職を目指す外国人の方に向けて、実務的な観点から必要な情報をまとめています。詳細な個別相談が必要な方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
就労ビザとは、外国人が日本国内で合法的に就労活動を行うための在留資格です。2024年11月現在、在留外国人数は358万人を超え、そのうち就労資格保持者は約38万人となっています。就労ビザは職種や専門性に応じて16種類に分類され、それぞれに固有の取得要件が定められています。
2024年の主な制度改正として、特定技能における新規4分野の追加が挙げられます。また高度専門職の受け入れ促進策として、2023年9月以降引き続き高度人材ポイント制における加点対象大学の大幅な追加など、評価基準の一部見直しも行われました。特に、デジタル分野での人材確保を目的とした要件緩和が注目されています。
2024年現在、日本には活動内容に応じて様々な種類の就労ビザが存在します。大きく分類すると以下のようになりますが、一般的に就労が認められる在留資格は合計16種類あります。
専門的・技術的分野の活動
特定の分野・技能に関する活動
身分・地位に基づく活動(永住者、定住者など。これらは活動制限がないため本来の就労ビザの意味とは異なります)
その他(特定活動など)
ここでは、主な就労ビザ(在留資格)16種類について解説します。
また、これらの他に、高度な能力を持つ外国人材を対象とした「高度専門職」という在留資格もあります。
| 対象職種 | システムエンジニア、通訳・翻訳、営業職など |
|---|---|
| 必要学歴 | 従事する業務に関連する分野の大学等を卒業しているか、10年以上の実務経験(国際業務は3年以上の場合あり)を有すること |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、3ヶ月のいずれか |
技術・人文知識・国際業務は最も取得者の多い在留資格で「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれ、IT技術者や通訳、マーケティング担当者など幅広い職種が対象となります。専攻分野と従事する業務との関連性が重視され、月額報酬は日本人と同等以上であることが求められます。
→技術・人文知識・国際業務ビザの詳細な内容はこちら
専門的な知識や技術を持つ高度外国人材の受け入れを促進するための在留資格です。ポイント制で評価され、70点以上で認定される高度専門職1号は、配偶者の就労や親の帯同、家事使用人の帯同に関する要件が緩和される場合があるなど多くの優遇を受けられる在留資格です。複合的な在留活動が可能で、80点以上獲得で最短1年での永住許可申請も可能となります。
→特別高度人材制度(j-skip)の詳細な内容はこちら
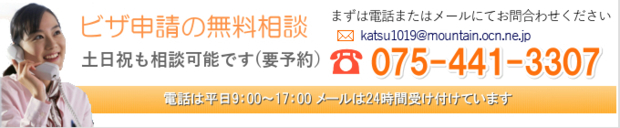
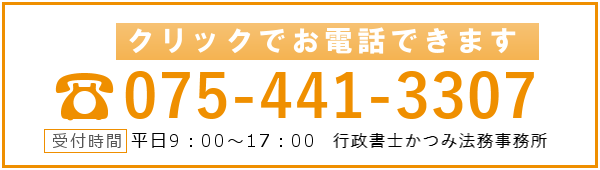
| 主な要件 | - 事業所の実体(独立した事業所の確保) - 事業の安定・継続性(収支計画の妥当性) - 経営規模要件(投資額500万円以上または常勤職員2名以上) |
|---|---|
| 在留期間 | 3ヶ月、4ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年のいずれか |
経営・管理ビザは日本で会社を設立して経営を行う場合や、工場長などの事業の管理職として活動する場合に必要な在留資格です。特に重要なのは事業の安定性と継続性で、申請時には詳細な事業計画書の提出が求められます。なお実務経験については経営と管理で異なり、経営は実務経験については要件とはなっていません(管理は管理について3年以上の実務経験)が、ある程度の経営経験があることが望ましくはあるでしょう。最初の在留期間は1年となることが一般的です。
→経営・管理ビザの詳細な内容はこちら
日本の法律に基づく資格が必要な在留資格です。外国法事務弁護士や公認会計士などが対象となり、それぞれの資格に応じた活動が認められます。
| 区分 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年まで | 更新制限なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能 |
特定産業分野における人手不足に対応するため、2019年に創設された在留資格です。2024年3月からは新たに4分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)が追加され、合計16分野となりました。特に人手不足が深刻な分野での外国人材受け入れを目的としています。
対象分野: 当初12分野でしたが、2024年3月に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」が追加され、合計16分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)が対象となっています。
各職種で必要とされる実務経験年数や資格要件が異なります。調理師は実務経験が通常10年以上必要とされますが、タイ料理についてはタイ料理人として初級以上の技能水準に関する証明書をもち、申請直前1年間本国においてタイ料理人として妥当な報酬を受け勤務していた場合には実務経験年数5年でOKになるなどの取り扱いもあるので事前に要件のチェックを怠らないようにしましょう。
→技能ビザの詳細な内容はこちら
| 必要資格 | 介護福祉士 |
|---|---|
| 日本語要件 | N2以上推奨(介護現場でのコミュニケーション能力必須) |
介護福祉士の国家資格を取得していることが必須条件です。N2以上の日本語能力は在留資格の要件とはなっていませんが、介護福祉士国家試験合格が要件となっており、介護福祉士養成施設入学時にはN2相当が必要であることから事実上の要件となっています。特定技能1号やEPA(経済連携協定)による来日者とは異なる在留資格となっていて、要件なども異なるのでそこは注意が必要です。
教授ビザは大学教授、准教授、助教などの高等教育機関での研究・教育活動が対象です。博士号取得者や相当の研究実績を持つ者が対象となる…と考える方が多そうですが、実は学歴などは要件とはなっていません(もちろん誰でもいいわけではないですが)。
| 対象機関 | 小学校、中学校、高等学校、専修学校等 |
|---|---|
| 主な職種 | 語学教師、インターナショナルスクール教師など |
教育ビザは大学卒業以上の学歴、あるいは行う教育に関する免許、語学教師の場合当該外国語により12年以上の教育を受けていることが必要です。
研究ビザは公私の機関との契約に基づく研究者が対象です。該当例としては、政府関係機関や私企業等の研究者が挙げられ、大学卒業もしくはこれと同等以上の教育を受けた後、従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験があるか、従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験が必要であるとされます。注意が必要なのは日本の大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究を行う場合は、教授ビザを申請する必要がある事です。
芸術ビザは作曲家、画家、彫刻家など、芸術活動を行う者が対象です。過去の作品や受賞歴などの実績が重視されます。
| 対象活動 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行活動 |
|---|---|
| 在留期間 | 最長3年 |
興行ビザはプロスポーツ選手や芸能人が主な対象です。興行契約に基づく活動が認められます。
在留資格によって必要書類は異なりますが、一般的に求められる書類として、パスポート、証明写真、在留資格認定証明書交付申請書、履歴書、学歴証明書、職歴証明書などがあります。
経営管理ビザの更新については会社の業績がかなり重要なポイントになります。また、就労ビザ一般に言えることとして雇用する会社が赤字決算が続いていたり、債務超過である場合は一般的な更新書類以外にも会社の業績に関する理由書その他の添付書類が追加で必要となる場合もあることに注意が必要です。
➡️ 就労ビザの申請条件詳細を知りたい方はこちら:[就労ビザの申請条件ガイド|学歴・職歴・実務経験の要件を徹底解説を詳しく見る]
本記事では日本で就労するために必要な在留資格、いわゆる「就労ビザ」について、全16種類の概要、特徴、主な取得要件、そして在留期間などを解説しました。
「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」といった代表的なものから、「特定技能」や「技能」といった現場を支える資格、さらには高度な専門性を持つ人材向けの「高度専門職」まで、多岐にわたる就労ビザが存在します。
特に近年は、特定技能の対象分野拡大(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の追加)や、技能実習制度から人材育成と確保を目的とした「育成就労制度」への移行(2027年頃までに施行予定)など、外国人材の受け入れに関する制度が大きく変化しています。
外国人材の採用を検討している企業の人事担当者の方々にとっては、自社の求める人材像や業務内容に合致する在留資格を正確に理解し、適切な手続きを進めることが不可欠です。また日本での就職を目指す外国人の方々にとっても、自身の学歴、職歴、スキルに合った在留資格の要件を確認し、準備を進めることが重要となります。
在留資格の申請や更新は提出書類も多く、審査も厳格に行われます。特に経営・管理ビザの更新や、制度変更の過渡期においては注意が必要です。この記事が日本の就労ビザに関する理解を深める一助となれば幸いです。
個別の状況に応じた具体的なアドバイスや申請サポートが必要な場合は、無料相談でご相談いただくこともご検討ください。
以下のページでは、ビザ申請の詳しい流れや、あなたと企業がそれぞれ準備すべき書類について、具体的に解説しています。
➡️ 次のステップへ:[申請手続きの完全ガイド(流れ・必要書類)を詳しく見る]
もし、複数のビザに該当する可能性があり迷っている場合や、ご自身の経歴で申請が可能か不安な場合は、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。専門家は、あなたの状況を正確に判断し、最も可能性の高い道筋を示してくれます。
➡️ [専門家への相談についてはこちら]
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。
➡️ 行政書士かつみ法務事務所の就労ビザ申請サポートについて知りたい方はこちら:[就労ビザ申請【京都】を詳しく見る]